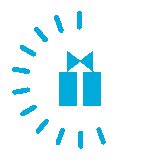- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様

お中元・お歳暮は必要ない?やめたいときの断り方なども紹介
お中元・お歳暮は必要ないのかや、やめたいときにどうしたら良いのか、失敗しないための情報をギフトモール所属のギフトのプロがわかりやすく解説します。そもそもお中元やお歳暮は何かなど、基本的な知識からしっかり確認していきましょう。
お中元・お歳暮は必要ない?
お中元やお歳暮が必要かを問うアンケートでは、必要と考える人より不要と思う人の割合がかなり多かったです。
しかし、相手が親しい人や家族の場合は、お中元・お歳暮をやり取りする人やしても良いと思う人が、しない人の割合を大きく上回っていました。
この結果から、儀礼的なやり取りではなく、大切な人へ日頃の感謝を伝える目的や繋がりを確認する手段としてのお中元・お歳暮は、必要と言えると思います。
お中元とお歳暮は両方送るべき?
お中元とお歳暮の両方を送らなければならないといった決まりはありません。
しかし、お中元とお歳暮ではお歳暮のほうが重要視されるため、お中元を送ってお歳暮を送らないとマナーに疎い印象を与えてしまうと思います。どちらか一方にする場合はお歳暮を送ってください。
お中元とお歳暮を送らない理由は?
アンケートでは、お中元やお歳暮を送らない理由として、儀礼的なやり取りに必要性を感じないからと回答した人が多かったです。
また、相手に気を使わせてしまい送ると迷惑になる点や、互いに送り合うやり取りが面倒になったことなどを理由として答えた人もいました。
そもそも、お中元・お歳暮とは?
お中元とは
お中元とは、一年の半分が過ぎた夏の時期に、お世話になった人へ感謝の気持ちや相手の体を気遣う想いを込めて送る贈り物のことです。
お中元の起源は中国で、道教の「中元」と仏教の「盂蘭盆会」が由来と言われています。どちらもご先祖様を供養する行事で、二つがミックスされたものが日本のお盆になりました。
そのお盆に、お世話になった人へ贈り物を渡すという日本古来の習慣が加わり、枝分かれした風習がお中元と考えられています。
お歳暮とは
お歳暮とは、その年お世話になった人に一年の感謝を込めて送る贈り物です。
年末年始に年神様やご先祖様へのお供え物を用意する古くからの日本の風習が、お歳暮の起源と考えられています。結婚で家を出た子供や分家の人が、実家や本家に送っていたのが始まりです。
江戸時代に武士が上司にあたる組頭に送るようになり、商人がお得意様に送り始めたことで、次第に現代のお歳暮に変化していったと言われています。
お中元・お歳暮のやめどきはいつ?
お中元やお歳暮のやめどきは、相手との関係性が遠くなるタイミングです。例えば引っ越しや転勤・転職、定年退職などを機にやめるケースはよくあります。
お中元やお歳暮は、一度送り始めたら少なくとも3年は続けるのが作法です。最初から来年はやらないと決めている場合は、「お礼」の名目で送ると良いと思います。
お中元・お歳暮をやめたいときの断り方は?
お中元やお歳暮をやめたいときに、相手に不快感を抱かせずに済む断り方をご紹介します。今後の贈り物がいらないことをトラブルなく伝えられるように、やめ方のポイントを確認しておきましょう。
お礼状で断る
お礼状でのお中元やお歳暮のお断りは、最も穏便で一般的な断り方と言われています。
贈り物はそのまま受け取り、「今後の贈り物はやめてほしい」といった意味合いの文言を入れた手書きのお礼状を送ります。
断りの言葉だけでなく、感謝やお付き合いの継続を願うメッセージを含めることで、相手を不快にさせずに済むと思います。
電話で伝える
親しい親戚など、お中元やお歳暮のお礼を電話で済ませられる間柄の相手ならば、今後の贈り物を電話でお断りしても気分を害されることはないと思います。
感謝や今後の変わらないお付き合いを願う気持ちを丁寧に述べたうえで、贈り物をお断りしたいことを伝えてください。
断り状を添えて返送する
お中元やお歳暮の贈り物を開封せず、お礼状で断る場合と同じような文面の断り状を添えて、上からきれいに包装しなおしたものを返送します。
お中元やお歳暮を受け取れない理由がある場合や、お断りしても何度も送ってこられるケースに適している方法です。
郵送された品物をそのまま受け取り拒否し、業者に持ち帰ってもらうのはとても失礼な断り方で相手を不快にさせてしまうため、避けた方が良いと思います。
「御礼」として同額以上のものを送る
送られてきたお中元やお歳暮と同額以上のものを、お断りの一文を入れたお礼状と一緒に「御礼」として送ります。
同額以上の御礼の品には、「気持ちは十分いただいたため、今後の気遣いは不要」の意味が込められています。
しっかり意思表示をしたい場合は、倍額以上の品物とわかるものを送るのがおすすめです。
お中元・お歳暮をいらないと言われた場合は?
お中元やお歳暮をいらないと言われたら、送るのをやめるのがマナーです。
「負担になってしまったようで申し訳ない」「厚意に甘えて季節の挨拶の品は控えさせてもらう」のようなニュアンスの手紙を返信します。
手紙を送るとかえって相手に気を使わせると感じる場合は、次に顔を合わせたときに伝えると良いと思います。
お中元・お歳暮を断るときのメッセージ例文
お中元やお歳暮を断る文面は、気遣いへの感謝が伝わる文章を相手に合わせた言葉遣いで書く必要があります。
親族や取引先の会社に送る場合の例文や、企業のルールとして廃止するときのお知らせの例文を見ていきましょう。
親族や親戚宛て
会社関係宛て
企業で廃止する場合
お中元・お歳暮におすすめの夏ギフト・冬ギフトも要チェック
お中元・お歳暮が必要ないのかや、断り方などがわかったら、御礼として送る品にもおすすめの夏ギフト・冬ギフトを確認しましょう。
次の記事ではセンスの良い商品ばかりをご紹介しているので、相手に喜んでもらえるものを簡単に見つけられます。ぜひ最後までチェックして、相手好みの贈り物を購入してください。